「登山初心者のマナー」を書きました
挨拶・ゴミ・トイレ・タバコなどの「最低限のマナーとエチケット」は登山を始めるときに知っておきたいところです
特に自分も含めて中高年のマナーの悪さが目立つようです
▼登山ではないですが、マナーの悪さを書いた記事です

登山では「自由」も大事な要素の一つ
「ルール」でがんじがらめになっている、自分の生活スペースからの「逃避(とうひ)」、これも大事な登山の目的です
しかし、残念ながら、「ひとり」のための山でないのも事実
そんなことから、ルールが、極端に少ない野山においては 、最小限のルールと、「そのひとのマナー」が、とても大事になってきます
その登山初心者に伝える「大事なマナー」をまとめてみました
登山のマナーとルール=▼ 目次==
- 家族のために山岳保険を
- 登山届(登山計画書)や書置きが必要(家族のために)
- バスや電車では臭いや荷物に気を付ける事
- 登山は登り優先・すれ違いでは挨拶を
- 山にあるものは採ってはダメ(高山植物は採らない)
- ラジオや熊スズも注意が必要
- ゴミはすてない
- 山のトイレの注意点
- 山で「水」は「超」大事
- たばこは山でも注意|愛煙家は肩身が狭い
- 中高年の登山マナー
- 登山の右側通行について
- 山では助け合い譲り合いが大事
▼初めての登山のやり方
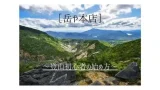
1 家族のために山岳保険を
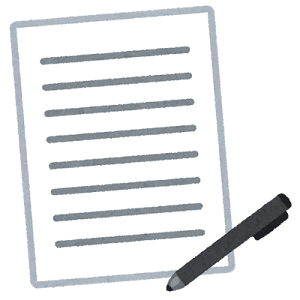
楽しく登山をしたいと思って山に行きますが、山は簡単に人を裏切ります
遭難をしたときに、山岳保険にはいってないとあとが大変
それは低山であっても、自分の家の、裏山と言われるようなところの登山であっても必要です
自分が助かるためというよりは、捜索するかたに迷惑をなるべくかけないため、そして、家族があなたの捜索に集中することができるようにするため、強く山岳保険に入ることをおすすめします ほんと大事
以前と違って、現在は遭難救助に特化したような保険(jROなど)が安い費用で入れます
また、どうしてもというかたには、1日だけの掛け捨て保険(何百円くらいです)もあります
いま入っている保険会社のかたに聞くと、掛け捨て保険があるかどうか教えてくれると思います
あれば簡単に加入できる場合があるので、ご相談するといいと思います
また、山岳保険を取り扱っている保険会社によっては、登山の形態を「軽登山」(ハイキングや縦走)と「山岳登攀」(いわゆるアイゼンやピッケルを使用するような場所)に分けているところもあるので、確認いただいたほうがいいと思います
個人的に入っているのは、「日本山岳救助機構(jRO)」と「モンベル保険」です
2 登山届(登山計画書)や書置きが必要(家族のために)
登山計画書を立てる事は、少し面倒ですが、とても大切なことです
計画書というような様式を使って計画を立てられれば最もよいですが、それが難しいようであれば、
- 行先(どのルートを使うか)
- 連絡用電話番号(つながらないところはそのように伝える)
- 同行者の名前と連絡先
- 帰る時間
くらいは家族にメモするといいと思います
警察に連絡する際の目安にもなりますし、その帰る時間を越えてしまう場合でも、警察に電話される前に、帰りの連絡をするようにすれば、連絡の習慣づけにもなると思います
登山届は最寄りの警察署や日本山岳協会で登山届の様式を提供しています
日本山岳協会の登山届をベースに作ったので、よければご利用いただくと嬉しいです
警察署の様式や手法はその署ごとにやりかたが違う(オンライン登録やFAXでの送付など)ので、確認が必要です
そのあたりも統一してもらえると、計画書が出しやすい環境になるので、お願いしたいところですね
3 バスや電車では臭いや荷物に気を付ける事

バスや電車に大きなザックを背負って、ストックを振り回すのは他人に迷惑になってしまいます
登山者でそのようなかたが多くなってしまうと、規制の対象となることがあるかもしれません
混雑の状況をみながら、座るときには、ザックは網棚か、膝の上に
ストックはザックに取りつけないで、いつも扱っているカサと同じように扱いましょう
楽しみにしていた登山で、テンションも高くなってしまうかもしれませんが、他人に迷惑をかけて、不快にさせてしまうのは自分中心で嫌われてしまいます
「自分と他人」の両方が楽しくなるようなイメージで登山に向うといいと思います
4 登山は登り優先・すれ違いでは挨拶を

登山道のマナーはいろいろあります
- 登山道をふさがない
- 後ろからの早いかたには追い抜いてもらう
- 自分のペースを守るのにもそうしたほうがいい
- 危険なところではおいこさない
このように、マナーはいくつかありますが、忘れがちなのは、上りが優先であるという暗黙のマナーです
※これには下り優先という考え方もあります ですが、大方(おおかた)は上りが優先という考えが多いと思います
狭い登山道で、上りと下りで交差するような場合は、下りの人がよけたり止まったりすることがマナー
どうしてそのようなマナーがあるか
その理由は下記のとおりです
- 下るほうが、体力にある程度余裕があり、下をむいているので、登ってくる人を発見しやすい
- 上りのひとは下を向いて一心不乱に登っているので、周囲への配慮するのは難しい
- 上りの人は頂上を目指すことに集中しているため、なるべく立ち止まることに抵抗がある(急ぎたい)
- 下りの人はすでに目的(頂上到達)を終えているので、心に余裕がある
以上理由から、上り優先のほうが、トラブルになりにくいのです
また、下り優先にしてほしい場合があります(高齢・障害などがある人の場合など)
そのときには早目に声をかけて、存在をアピールして、下りを先に通してもらうようにしたいです
また「大人数のときのすれ違い」も、リーダーの判断で、全員をいっぺんに通さないような工夫をしたりしないと、トラブルの元になります
お互いを思いやる気持ちを大事にして、なるべく挨拶(あいさつ)をすると、お互い気持ちよく山に登れると思います
※あいさつも良く思わない人もいるので、し過ぎも禁物です
↓このような道具を使って、登山に余裕を持たせるといいです
(スポンサーリンク)
メンズ
ウィメンズ
(PR)
それでも原則は上り優先なのです
5 山にあるものは採ってはダメ(高山植物は採らない)
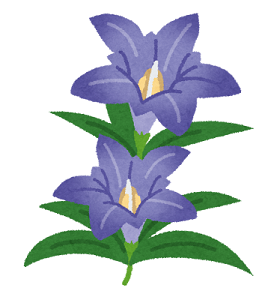
まず動植物(特に花が多いですが)を持ち帰るのは厳禁
どうしても過酷な環境なのに、可憐な花が咲いていると手を掛けたくなりますが、その行為はほとんど禁止されています
写真撮影にも注意が必要
特にロープ柵がある場所は、関係者や使っている方々が必要だと思ったから張ってあるので、「立入らないのがマナー」
「石」などの無機物も、原則持って帰ったり、移動させてりはダメ
石くらいいいじゃないかと思うかもしれませんが、石もまた、「その山域の観光資源」
気を付けるようにしたいです
また、動物にはエサをやらないことは「特に大原則」
野生の動物には、人間は怖いものと認識してもらわないと、互いが不幸になってしまいます
特にサルは、頭もよく、個体も多い場合があるので、特に慣れると怖いです
そして、下りなどで、登山道ではないところをショートカットしたくなるときもありますが、環境へのローインパクト(自然への負荷を最小限にすること)を考え、登山道ではないようなところはあまり使わないようにするといいと思います
※自分もショートカットしたくなるので気を付けます
その山域で人が多くなると、このような環境への負荷による環境破壊が顕著になってきます
高山植物というのは、氷河期に北から日本にやってきて、その後気候が暖かくなってくると、逃げ場がなくなって高所に上がっていきました
言わば陸の孤島(ことう)に取り残された種類で、そこしか住むところはありません
庭に飾りたい・だれかに見せたい・記念にしたい・疲れたので楽をしたい などといろいろな理由はありますが、山にあるものはあるがままに・・・です
6 ラジオや熊スズも注意が必要

ラジオや熊スズの音もいろいろなかたから、意見があるようです
通常ひとが多い場所では、音は迷惑となってしまいます
しかし、ラジオや熊スズは野生の動物に会わないようにするためのもの
その使い分けが大事です
原則は音をだすことが必要ですが、場所によってはポケットの中にいれておくような臨機応変さが必要です
↓このスズはワンタッチで音がならないようにできます
スポンサーリンク
7 ゴミはすてない

これは今の世の中では、常識中の常識
山でも街でもこのマナーを踏み外すと、人としての良識を問われます
8 山のトイレの注意点

トイレ以外での大便(自然に排便すること)は特に注意したいです
また、山にあるトイレは注意書きをよく読み、ルールに従って使わないと、今後撤去されてしまうことがあるので、注意です
街でも、トイレが近くになくて苦労した経験は誰にでもあるのではないでしょうか
それは山でも同じです
みんなが、ここでトイレがあるととても助かるのに・・・・と思っているので設置してあります
トイレ設置を持続してもらうためにも、ルールを守って貸してもらうという気持ちでトイレを使うわないと、管理が大変になり撤去されてしまうこともあります
9 山で「水」は「超」大事

山では、「水の一滴は血の一滴」と言います
山で水を確保することに、どの山域や小屋でも血眼(ちまなこ)になって確保しています
それを粗末にすることは、他人からみればかなり嫌な思いにさせてしまいます
山で水の量には限度があります
よく考えて使わないと、生命にもかかわる問題となってしまうので、気をつけるべきです
10 たばこは山でも注意|愛煙家は肩身が狭い

いまは、愛煙家には住みづらい世の中になっているようです
最近では分煙、禁煙がすすんでおり、昔のようにどこでもタバコが吸えるような環境ではなくなりました
特に子供がいる環境では全面禁止
タバコを吸っていると知られると、おくさま方から「一挙手一投足」を見られているとこを肝に銘じるべきです
直接言ってくれるかたは、まだ優しいです
普通は「オモテではなにもいいません」
でも「ウラではかなりの意見を話している」ことは良く聞きます
それは山でも一緒
いまは、女性ばかりでなく、男性でも嫌いな人は多くなりました
お金を払って、法律も守って吸っているのにそのような目で見られるのは、まったく嫌ですよね
そして、周りに気を配ってタバコを吸っている愛煙家の方々も、それなりに多くいるのは知っています
しかし、一部のかたのせいでやっぱり愛煙家のイメージは悪くなってしまうのが現状
隠れている吸っていれば目立ちませんが、オープンで迷惑をかけている人は特には目立ちます
お互いがお互いのことを思いやりながら、共存していけるといいです
[登山のマナーが悪い!?]愛煙・禁煙どちらにも聞いてほしいマナーの知識

中高年の登山マナー
よく言われることですが、「中高年の登山マナー」が悪いと言われることが多いです
自分も中高年なので、この意見は反省しなければならない事柄(ことがら)
「中高年の登山マナー」で検索すると、ネガティブな記事が結構あります
例えば
Yahoo!知恵袋の「登山マナーの悪い中高年についてどう思いますか?」という記事
登山マナーの悪い中高年についてどう思いますか?挨拶はしない、下りなのに我が物顔に登山道を歩く、ストックをふりまわす、高山植物保護の為のロープを全体重をかけて登っていく等々全員がそうではありませんが、あまりにもひどいと思ったので書きました
出典:Yahoo!知恵袋
確かにこれはちょっと残念
これは中高年と言わず全員がそのようなマナーは守ると、みんなが気持ちよく登山できるのでは・・と思ってしまいます
ここで、考察
反論ではないですが、個人的には、中高年だけがマナー違反というわけではないと思います
自分が山に登っていて感じる印象は、老若男女の区別なく、マナーが良い人、悪い人がいます
ですが、オンラインのような拡散しやすい情報メディアは、中高年の人はどうしても疎い(うとい)
そして、それらが得意な若い人達の意見がよく目立つ(めだつ)ため「中高年のマナーが悪い」という意見を良く聞く・・・のではないかと考えます
逆に昔は、「イマドキの若いもんは・・・」という意見のほうが多かったと思いますしね
「中高年」は「若い人」からすれば「親世代」
子供のマナー違反を注意するのは当たり前ですが、中高年は親なのですから、子供の手本となるような行動をしたいと思っていきたいと思います
登山の右側通行について
よく言われるのは、登山道は右側通行が基本ということ
個人的に言えば、これはどちらでもいいと思いますが、人が多いところではそのようにしたほうがいい場合もあります
場所によって、看板などで、「右側通行」をお願いしているところもあります
例えば尾瀬はそうのようです
6. 木道・歩道を歩きましょう
木道・歩道を歩きましょう
湿原を保護するための木道です
湿原に踏み込まないことはもちろんですが、カメラの三脚などを湿原に立てないことも大切です
右側通行、登り優先、歩行中の禁煙にご協力をお願いします
出典:尾瀬保護財団
そのような「きまり」がないところは、お互いの安全が確保できるようなすれ違いができるといいと思います
11 山では助け合い譲り合いが大事

山小屋などで、お金さえ払えば、ほかの人より良い食事や、良い環境を手に入れることができる、と考えているかたがいらっしゃいますが、それは難しい
山では助け合いが肝心なのです
一部の山小屋ではそのようなことはあるかもしれませんが、基本は皆同じ環境を受け入れることが、山では必要
山小屋はたいてい過酷な環境の中継地点として建設されています
そのような過酷な環境ではみんな平等
みんな助け合って使用させてもらっているという考えを根底において、助け合いの精神で山小屋を使うようにしたいです
それは山小屋の周辺ばかりでなく、テント場でも同様です
他人といざこざになって、後味の悪い登山になってしまわないように、このような人の多いところでは特に気を付けましょう
マナーとは人それぞれ、自分で管理すべき他人への思いやりです
思いやりを忘れずに楽しい登山ができるといいと思います



![[シーダブリューエックス/ワコール] スポーツタイツ スタビライクスモデル (ロング丈) 吸汗速乾 UVカット メンズ](https://m.media-amazon.com/images/I/41XcD00FjUL._SL160_.jpg)
![[シーダブリューエックス/ワコール] スポーツタイツ スタビライクスモデル(ロング丈) 吸汗速乾 UVカット[レディース] HZY149](https://m.media-amazon.com/images/I/31A6VPZ0oJL._SL160_.jpg)
