Warning: Undefined property: stdClass::$ByLineInfo in /home/soiya78/airisu745.info/public_html/wp-content/themes/cocoon-master/lib/shortcodes-amazon.php on line 666
単独登山の危険をを紹介します

最近「登山の事故」が多く、それがニュースになることも多いです
事故があった場合、その対処(たいしょ)が難しい「単独(ソロ)の登山」は、どのサイトでもあまりオススメしていません
ソロの場合は登山装備もやや重くなります
逆に、オススメはしていませんが、それでも「ソロの自由」がいいと言うサイトもあります
最近は女性でもソロ「単独」での登山をするひとをよくみかけます
また、最近のニュースでは
山岳遭難死・不明319人 4年連続300人超、単独登山が6割
出典:日本経済新聞より
という、ソロの危険性を打ち出している記事もあります
このサイトでも、ほかのサイトと同じく、ソロ登山は推奨しません
でも逆に、自分はソロ登山が好きなのも確かです
どんな人でも、登山をしていると、単独での登山(ハイキングなども含む)をするときがあると思うので、そんなときの参考に、自分のソロ登山をする場合の考え方を書きたいと思います
[単独登山の危険]=▼目次==
▼関連記事

[単独登山の危険]ソロのときの注意点
ソロ登山の時の注意点は2つ
どちらの注意点も最終的にはやることは一つなのですが、異なる立場の考えかたを書きましたので、参考にしてください
家族の理解
自分が単独のときに、一番に気を付けているのはこれです
単独で何かあった場合、探しに行くのは家族です
山岳会などに入っていれば、会での捜索もありますが、それでも一番心配をかけ、心身ともに疲労を与えてしまうのは、家族ですね
特に自分のように40~50代なら、責任がとても重く、倒れてはいけないことは重々承知だと思います
特によく言われる三大疾病の内、「心臓疾患」は40代から危険なエリアに入ってきます
自分は、家族に心配をかけないように、簡単なプレゼンをします
山行ごとではなく、夏と冬、季節の変わり目に行います
- 1) 安全器具を説明
- 2) 登山計画書を出す
- 3) 登山計画書とは別に必ず帰れる時間を説明する
「1)安全器具を説明」 の場合を説明します
これは自分の安全器具は分かりやすいものだけを説明して理解を得ます
たとえば、
- GPS
- その山域で電話がつながるかどうか
- 熊スプレー
- 笛
- ビーコン
- ヒトココ(探知機器)
- アバラング などなど
これらを、なるべく分かりやすく家族に説明し、これがあるから、危ないときもリスクを減らせる!!・・・と説明をします
説明しても、山のことが分からない家族は半信半疑ですが、説明しないよりは理解を得られやすいです
「2)登山計画書」を出すについては、「計画書」を出して、そして簡単に家族に説明します
説明するのは、
- 行く山域
- 行く時間
- 帰る時間
この3つです
それ以外は説明しても難しいので、ある程度の時間まで連絡が無い時には、「計画書」警察に渡してもらうようにするといいと思います
この「警察」という言葉を自分で口に出すことによって、家族もちょっとだけ安心しますし、自分も心が引きしまります
(警察と言うと、逆に家族が不安になる場合もありますので、家庭の状況で判断してください)
「3)登山計画書とは別に必ず帰れる時間を説明する」について説明します
これは、登山計画書に帰る時間は書いてありますが、確認の意味をこめて口頭で家族に伝えます
自分の雰囲気では、これが一番安心を与えているような気がします
具体的に言うと、
・遅くても○○時には戻る(この遅くてもが大事)
と言います
この一言が大切
これを言うと、自分も少なくともその時間までには戻るように頑張るし、何かトラブルがあった場合は、その時間前には家族に電話をするようになります
家族も、その時間が何かのアクション(警察に電話をするなど)のきっかけになるので、これを伝えることは、とても意味のあることだと思います
これらのことは家族の理解を得る上では、とても重要なことです
なにより登山は、誰がどう見ても趣味の一環でただの「遊び」です
そんな遊びをするには、まず一番に、家族の理解が必要なのです
登山で自分がギリギリ戻れるところはどのあたりか、そこを意識する
10代や20代の人も家族の事を考えてほしいと思いますが、自分が20代だったころのことを思い返してみると、家族のことなんて全く考えていませんでしたね・・・・
逆に迷惑ばかりかけていて、40代になってから考えると、かなり危険なことをしていたと思います(20代の頃は登山をしていませんでしたそのため危険なことというのは、もっと別なことです・・・・)
体力と気力が充実していますから、何でも出来るような気がするし、実際できます
40代と「安全マージンの考え方が根本的に違う」ので家族のことはあまり考えられないですよね
そんな若い方への注意点は、とりあえずどんな形になったとしても戻って来ることを意識することです
有名な登山家、14サミッターの竹内洋岳さんは、最後の頂上を目指すプッシュの時、まずここで行くと自分が戻れるかどうかを、一度「後ろを見て」判断するということです
そして、「絶対帰ってこられる」と思えたときだけプッシュする・・と言っていました
片道切符では、帰ってきても「自慢できません」し、なによりカッコよくありません
「竹内さん」はプロですから、そのあたりはシビアに考えています
すごいのは、疲れがピークで、高度障害が出ているその極限の環境と心理のときに、そういう判断ができるということがスゴイと思います
自分は「竹内さん」のマネはできないので、具体的に「戻る条件」を下界で考えから山に行きます
例えば、どこに何時に辿りつけなければ戻る、とか、食糧がここでこれだけになった場合は戻るとか、決めておきます
冬では、雪崩(なだれ)の評価の仕方(チェックリスト)がしっかりできているので、それを判断に使っていて、いかに晴天で気持ちよくて登りたくても帰るようにしています
最近の事故では、有名な山岳会の元会長さんでも雪崩(なだれ)に会ってしまった・・・というニュースもあって、自然を判断する難しさをより痛感してしまいます
そういった判断は、山に行ってから決めようと思っても、もうちょっとだけ・・という気持ちがどうしても出て来てしまって、なかなか踏ん切り(ふんぎり)がつきません
竹内さんはどういう形で、そしてどういう決め方をしているのでしょうか
自分が雑誌で見た限りでは、そこまでしか書いていなかったので、詳細は分かりませんが、詳細に聞いてみたいですね
[単独登山の危険]ソロにはこんなデメリットがあります
ソロの場合のデメリットはたくさんありますが、その中で特に注意が必要だと思うデメリットをあげてみます
野生動物に馬鹿にされる

スポンサーリンク
「馬鹿にされる」というのは、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、その名のとおり、ソロで行くと、クマ・シカ・サル・野犬にバカにされることがあります
クマやシカはたいてい1匹なので、すこしはこちらを怖がってくれますが、サルと野犬は1匹でない事が多いので、ひとりの時は「威嚇(いかく)」されたりします
最悪は襲われる可能性もあります(自分はまだないですが・・)
特にサルは頭がよく、こちらを襲う(おそう)か襲わないかは人間のように判断するので、食べ物などを外に出して置くと襲われる場合があると思います
シカ(カモシカ)も人間に慣れているので、ビックリするくらい近くに寄ってくることがあります
人間の近くを通って、肝試し(きもだめし)をしているような若いシカにも会ったことがあります
また、あまり登山のときは会いませんが、イノシシも注意すべき動物です
イノシシは、遭遇したら、駆け引きはしません
とりあえず何も考えず体当たりをしてくるので、注意が必要です
自分はイノシシに襲われたことはありませんが、自分の家の周辺ではよく見られ、襲われた人の話しを聞くと、とても危険だということが、十分伝わります
クマも危険です
▼対策品はこちらをご覧ください
最近の野生の動物は、学習や、人間の環境への順応が進んでおり、これまでのような古い対応では追い付かなくなってきています
登山で野生動物に会ったら、野生動物が人間ならどうするか・・・ということを考えながら行動することが大切だと思います
ソロは判断が偏り(かたより)がち
ソロは当然「ひとり」なので、「3人寄れば文殊の知恵」のように、相談して、いい案を考えることはできません
全て自分で判断して行動します
体調が悪いと冷静な判断ができないことがあるので、体調には特に注意が必要でしょう
そのためには安全を確保する装備が大切です(下記の「ソロの時に持って行きたい道具・装備」で説明します)
また、登るか、戻るかを決定するのに、客観的な判断をするようなツールも必要になってきます
例えば、雪崩(なだれ)の判断の時は、雪の状況チェックする項目に○を付けていって、その点数で行くか行かないかを決めるような様式を使ったり、下界にいる時に、天気の条件、自分の体調などのボーダーラインを自分なりに決めていくと、判断がしやすいと思います
装備が重くなる

スポンサーリンク
共同装備が必要になる登山の場合、装備の分担(ぶんたん)がなくなるために、必然的に装備が重くなります
たとえば、ストーブやテントなどは、2人の場合は分担して持てますが、1人の場合は、全て1人が持つようになります
このデメリットは大きいですよね
そのために、軽量化の技術が必要になってきます(軽量化については後日書きたいと思います)
交通費がかかる
装備の重さと同じです
山域までに自動車を使う場合、乗り合わせの方が断然安いです
公共機関などを使う場合はこのようなことはあまり起こりませんが、それでもタクシーを使うと2人のときのほうが安いので、このあたりはソロの時は、あきらめなければなりません
[単独登山の危険]ソロの心構え
ソロは慣れてしまうと楽しいものです
しかし、慣れは油断につながります
山でソロというのは、誰も注意してくれないので、複数のときよりは「常に心を緊張」させないといけません
デメリットに聞こえますが、これは逆にメリットで、複数の場合、注意しても動きが荒くなる傾向があって、自分で油断していることがよくわかります
人間も集団で生活している動物ですから、集団でいると安心してしまうんですね
よく大勢でいる場合、みんながそちらに行くので、自分も行ってしまうということは、この心理が働いています
ソロの時は、この油断が複数のときよりは少なく、登山に必要な集中力を鍛える(きたえる)にはもってこいです
そのため、せっかくその集中力を養う絶好の機会を、「ソロに慣れてしまうことでその機会を失う」のは、とてももったいない気がします
一番は、ソロ登山をすることで、ソロでも複数でも同じような集中力を出せるように鍛えるということが自分は大事だと思っています
そのため、あまりソロばかりをやっていると、それに慣れてしまうので、「できればソロとパーティ登山を半分くらい」にすると良いかなと思います
かなり特殊な考えですが、自分はこんなことを考えて「ソロ登山」をしています
[単独登山の危険]ソロの時に持って行きたい道具・装備
装備は通常の登山とあまり変わりありません
その中でも、今回はソロには特に重要だと思われるものを挙げてみます
GPS・コンパス・地図
これは必須なことは十分理解してもらえると思います
どんな時でも必携(ひっけい)です
クマスプレー
野生動物と出会いがしらに会うと、すぐ出せないので、怪しい場所に来たら、先に出して置くなどの工夫が必要です
あるサイトでは、持っていると、クマなどに会っても冷静に対応できる、とありましたので、お守りとしても有効です
ヒトココ(探知機)
最近はある程度浸透(しんとう)しているような気がしますが、まだまだメジャーではないようです
遭難などのときには、IDナンバーを家族に教えておくだけで、見つけてもらえる可能性がグンっと上がるので、持っていて損はないです
アバランチビーコン
冬登山に雪崩(なだれ)にあったときに使う、「信号を出す装置」です
雪崩に埋もれたら、ここから信号をだして、救助を待ちます
アバラング
これも冬限定商品です
ブラックダイヤモンドの「雪崩用緊急呼吸確保器」です
雪崩に埋もれると、口のまわりには、呼気で雪が一度溶けて、その後再凍結(さいとうけつ)して「氷の膜」を作ってしまいます
その膜が原因で、二酸化炭素が充満して窒息(ちっそく)するのですが、これは呼気をお尻の方に逃がすので、長い時間窒息しない(噂では1時間くらいは大丈夫のようですが・・・)という製品です
レインウェア
ウィメンズ
メンズ
これは春夏秋用です
なぜ持って行くかというと、風と雨を防ぐため
「特に風」
ツェルトもほしいところですが、とりあえずはレインウェアが必須です
ヘッドライト
これはパーティ登山のときでも必須です
遭難したとき、ビバークするには特に必要になります
自分は仕事柄よく使いますが、聞いたところによると、持っているだけで警察に職務質問をされるようです・・・・どうなのでしょうね
調べたところによると、「軽犯罪法第1条3号 侵入具の携帯」の適用を受けてしまうらしいです
ナイフと同じ考えで、登山のような目的があれば良いので、普通の人には問題がないはなしですね
食糧
これも必須
お昼前に帰って来るような登山でも、遭難するとソイジョイ1個あるだけでかなり違うと思います
自分は遭難したことがないので、そのつらさはまだ味わったことはないですが、先達(せんだつ)に聞くと、かなりつらいということ
忘れないようにしてください
[単独登山の危険]どうしてソロになるのか
自分は怖がりで、幽霊などを信じてしまうタイプです
実際、山中で鳥肌(とりはだ)が立つような経験は何回かありました
ソロの登山、特に夜のソロはある程度慣れないと、かなりビビリます
慣れてくるとそうでもないのですが、久しぶりに夜のソロ(まだ夜はソロでしか行ったことがありません)のときは、慣れた山でも、そして何回行っても慣れません
それでもソロがいいです
その理由を説明します
友達が少ないのも理由のひとつ

スポンサーリンク
自分は悲しいかな、友達がいません
いませんというと語弊(ごへい)がありますが、かなり少ないです
友達がいないから、一人でもやれる登山をやっている・・という逆説(ぎゃくせつ)的なことになっていることが実際のところです
自分の場合は、登山をやっていてソロになる・・・のではなく、人生がソロなので登山もソロ・・・ということになりますね
完璧主義で性格が細かい

スポンサーリンク
これも大きな理由です
○○時ぴったりに出発して、○○時までに家に帰る・・・のようにキッチリ決めている計画を完璧にやりたい時があります
そんなときは必然的にソロになります
また、誰を誘っても賛同(さんどう)を得られないような面倒な山行計画も、ダレも行ってくれないので、ソロになります
誘っている時間が無駄かな・・と思ってしまうので、それも最初からソロで考えてしまいます
サバイバル登山家の服部文祥氏も著書でそのようなことを考えているようなので、ソロの人は、多かれ少なかれ、そんな心理が働くのだと思います
精神的なところで上を目指したい
独りで山にいくのは、普通考えると、とても怖いことです
集団の心理も働いて、自分も毎回行くまでがとても面倒というかとても不安です
出発してから、しばらくして、夜という環境に慣れてくると、そんなに怖くはなくなります
感覚的には、肝試しをしているような感覚です
特に夜は「The肝試し」ですね
何度か、山中で後ろから追い抜かれたことがありますが、とてもビックリします
暗くてよく見えませんでしたが、あいさつをしているので、お化けではないと思います
でも不思議なことに、山頂に行くとその人はいないのです
別のルートに行ったかもしれませんが、そんな雰囲気はないように思えます
そう考えると、毎回不安になって、後ろを何度も確認してしまいます・・・・
うーん精神が鍛えられますねー
まとめ的な理由:ソロは恰好が良いから

スポンサーリンク
よく考えると、最終的には、全部これが理由になるような気がして付け加えました
ソロというと、周りのひとからカッコいいと思われるような気がするから、ソロで登山をするのだと思います
なんとなく、自分の中では、「仲良しは恥ずかしい」と思う部分があるみたいです
ソロ登山をやって、カッコいいと思われるためにソロをやる
正直なところこれが最大の理由でしょうか
以上自分のソロについてのお話でした

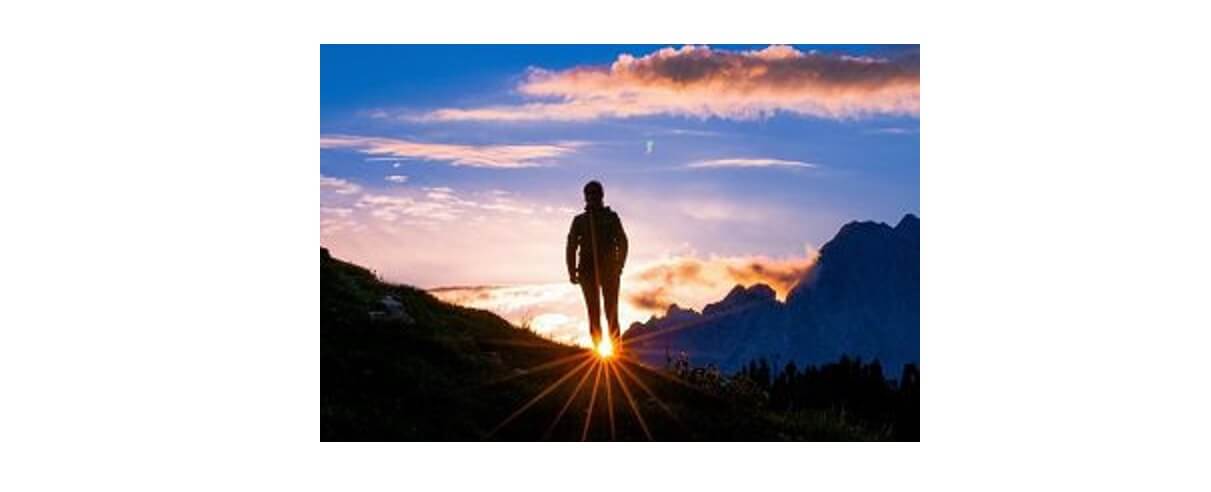








![[ザノースフェイス] ハイベントレインテックス レディース プロバンスブルー L](https://m.media-amazon.com/images/I/41aaEodsXNL._SL160_.jpg)
![[ザノースフェイス] レインテックスプラズマ ハイリスクレッド×ブラック L](https://m.media-amazon.com/images/I/31+DVH2gHKL._SL160_.jpg)
![PETZL (ペツル) TIKKINA ティキナ E91AB ブラック メーカー説明書付き(日本語あり) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51yqamgFwVL._SL160_.jpg)
