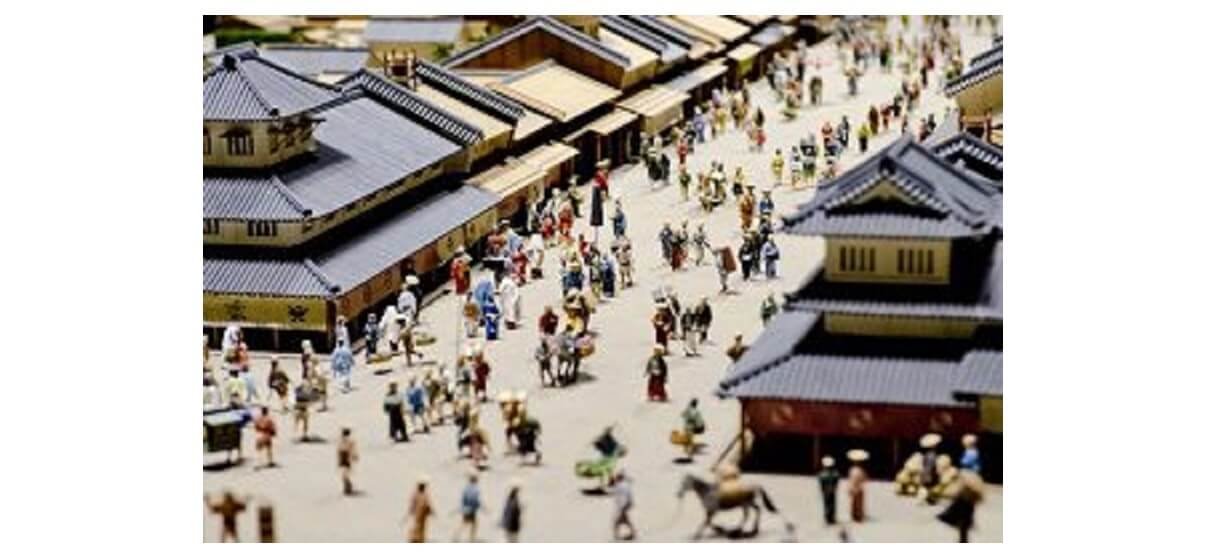【旅人の服装】服部文祥氏から学ぶ江戸の登山|登山初心者の読み物
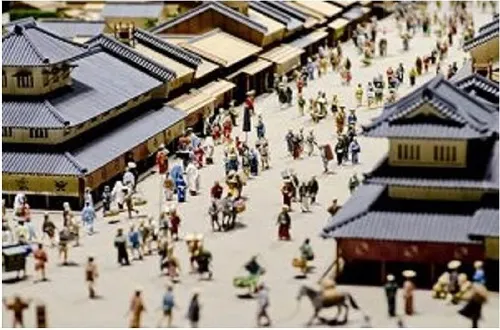
自分がよく行くお寺は浄土真宗で、その開祖の親鸞(しんらん)の銅像が寺の門のところに立っています。
ここの親鸞様は少しいかめしい顔をしていて、旅人の恰好をしています。
昔の江戸時代の旅人の恰好と言えば、草鞋(わらじ)に脚絆(きゃはん)、菅笠(すげがさ)が頭に浮かびます。
江戸時代、旅というと、整備されているところは少なく、ほぼ登山道のような道中だったと思います。
東海道のようなメジャーな道以外は、ケモノ道のような、一度道を間違えると、どこにいるかわからないような道だったのでしょう。
まるで現代の登山と一緒です。
少し興味が出てきたので、調べて見ることにしました。
▼関連記事

旅人の装備 調査はじめ
そういえば、自分の好きな服部文祥氏も、著書「百年前の山を旅する」で100年前(明治初期)の脚絆(きゃはん)や菅笠(すげがさ)といういで立ちで、山を巡って登山をしています。
そのときの服部文祥氏がやたら明治時代の服装が似合うので、なんとなく笑ってしまいましたが、そのいで立ちとその装備で、残雪があるところや、登攀が必要なところを行けるかと言われると、戦慄(せんりつ)が走ってしまいます。
明治の人たちは、そのくらいの装備と、そして知識とその体力のみで旅ができていたのでしょうか。
今回調べてみるのは、服部氏が山行を行ったスタイルの100年前から、さらに100年さかのぼって200年前の江戸時代を調べてみました。
今から200年も前のころはどんな旅のスタイルだったのでしょうか
江戸時代の旅は命がけ
江戸時代の旅はまさに命がけでした。
旅をしたくても、危険がいっぱいです。
山道での遭難や追いはぎ、そして病気や怪我などはどれも致命的で、確率から言えば旅にでないでいたほうが、生きる確率はかなり高確率を保てたと思います。
しかし、いまの登山家と同じで、退屈な日常に飽きてくると、危険を求め始めるのが人情というわけで、それはいつの世もかわらないようです。
それでも、江戸時代は、旅の出発の時に、今生の別れのように皆に見送られるようなことがあったそうで、それは現在の登山にはないですね。
見送られるというと、戦争の徴兵を思い出しますが、少なくとも江戸時代はじめごろの旅は、戦争に行くくらいの危険度はあったのでしょうか。
旅の必需品 手形の取り方
江戸時代は旅行をするために、「通行手形」といわれるパスポートのようなものが、旅には必要でした。
手形は一般の人は土地の名主などから手形をもらえたようです。
当時は原則、藩(今の県くらいの大きさの独立した国)から藩への移動は禁じられていました。
道路や通行するような場所に、関所や番所といわれる関門を設置して、人の往来を制限していました。
しかし、実際は、御伊勢参りや富士山、善行寺などの霊場への旅はとても盛んにおこなわれていたようです。
とくに江戸後期は、旅(登山)は娯楽の一つとして、民衆に浸透していました。
また、手形には、旅する人の素性や、旅の目的、行先を始め、髪形、顔・手足の特徴などが細かく記載されています。
この記載内容と一致しなければ、関所は通れなかったようです。
江戸時代 旅の道具
いよいよ本題の道具の紹介です。
まず、江戸時代においても、旅に必要なことは、本を見て勉強をしていたようです。
以下は1810年に刊行された「旅行用心集」という本。
当時の旅の必需品の一つだったようですね。
スポンサーリンク
現代訳です。
江戸時代 旅人の服装について
旅(登山)の服装は以下が基本のようです。

参考:私のゆるゆる生活(http://mnnoblog.exblog.jp/22048159/)
特に草鞋(わらじ)はとくに重要で、3日で1足はきつぶしたそうですから、何足も無ければ旅にはなりません。
有名な街道(東海道など)は茶屋などで、わらじを買うことはできましたが、茶屋などがない場所では草鞋がなくなれば大変なので、持参しなければなりません。
現在の登山おいても 「サバイバル服部文祥氏 山道具まとめ」
で服部氏が話しているとおり、足回りは最重要装備の一つです。
これが無ければ全く論外なのです。
草鞋(わらじ)は奈良時代に草を編んで作るクツが大陸より伝わったそうです。
このころは稲作も盛んでありましたので、それで出てきた、稲わらを生活用具の材料に使用するには打ってつけだったのです。
そして、その稲わらが草を編んで作るクツの材料に使われるようになって、室町時代には「ワラジ」と呼ばれるようになったといいます。
旅に使う道具
いろいろありましが、よく使われるものとして、以下のようにまとめました。
携帯用 日時計
スポンサーリンク
南中したことを図るためのもので、別名「正午計」とも呼ばれています。
昔は腕時計の代わりに日時計をもっていたのですね。
確かに現代もそうですが、時間がわからないと、かなり苦労しそうです。
しかし、サバイバル登山家の服部氏も言っていますが、山で時計が無くてもなんとかなります。(自分もそうです)
だいたいの時間がわかれば、ある程度は山では過ごせるのです。
時計が必要なときは、下山後のバスの時間や、帰る時間を気にすることに使用します。
つまり下界に降りるために必要なのです。
江戸時代、携帯日時計は高価だったと想像すれば、お金持ちのビジネスマンでとても忙しいひとが使っていたのでは・・と推測されます。
江戸時代の筆入れ 矢立て
スポンサーリンク
参考:現代版矢立て
矢立てとは、現代で言うとメモをする鉛筆のようなものです。
長い柄が筆入れで、丸い容器に墨を染み込ませた墨ツボがセットになっていて、持ち運び出来るようにした筆記用具です
自分もメモを取らないと、普段でさえ1時間前のものを思い出すのは苦労します。
ましてや山に登っているときにはメモを取らないと大変です。
記録をとるために、メモを取っていますが、やっぱり登りのキツイところや、緊張を強いられるようなところは、メモを取ることを忘れてしまいます。
忘れてしまうというか、それどころではないというのが本音でしょうか。
昔はそれが筆であったようですから、メモをするのも大変ですね。
方位計
スポンサーリンク
参考:現代版 PL アンティーク風 AUTENTICO アンティークコンパス 62706
方位計は現在の方位磁石とほぼいっしょですね。昔も今も方位が分からないと旅はできなかったようです。
その当時の方位計を見ると、意外に今の物と大きくかわりはないようにみえます。
海では盛んにつかわれていたようですが、小さなものは、陸路でも使われていたのではないでしょうか。
こういうものが多くなってきたということは、一般的に旅ができるようになってきた証拠ですね。
小田原提灯
スポンサーリンク
参考:現代版 小田原提灯
参考の 現代版 小田原提灯は派手でイメージと違うようなところがありますが、テレビでよく見かけるいわゆる時代劇などで、商人などが使用人といっしょに夜歩いているときに使用人がもっている提灯が 小田原提灯 です。
実家に小田原提灯ではないですが、提灯がありました。
しかし、火を点けてもかなり暗かったように思えます。
昔の方はあの暗さでも前にすすめたのですから、すごいですね。
あかりを付けても、3mくらい先しか見えないです。
確かにあれを掲げて、暗闇をすすんでいっていくと、創造力ばかり先立って、ヤナギも幽霊に見えてしまうと思います。
それからすれば、現在のヘッドランプは何倍明るく、文明の利器のすごさがわかりました。
振り分け弁当
出典:Amazon
参考:現代版 竹弁当箱
2つの竹の弁当箱をヒモで結んで、それを肩にかけて持っていく、通気性がありとても軽い弁当箱です。
現在も似たような弁当箱は作られていて、その機能性は今も昔も変わらないようです。
携帯用火打ち金
スポンサーリンク
参考:現代版 火打ち金
硬い石と火打ち金をたたきこすることによって火花を飛び散らせ、火種に火を点ける道具です。
よく「暴れん坊将軍」のめ組のサブちゃんが、おかみさんにお出かけの際に切り火をやってもらっています。
火種を作るだけではなく、切り火は厄払いや邪気を祓う日本古来の風習でその道具として、重要な役割をもっています。
煙草入れ
スポンサーリンク
参考:現代版 煙草入れ
キセルを入れる筒と、財布のようなタバコ入れがセットになっているものです。
今もそうですが、粋な江戸っ子のワンポイントとしていろいろなタバコ入れがあったようです。
印籠(いんろう)
スポンサーリンク
参考:現代版 印籠
印篭は、そう、あの黄門様が使われているあの印籠です。
腰に下げる長円形の小さい箱で、箱をヒモで貫き通して、ヒモを締めます。
そして、先に「根付け」と呼ばれる帯止めをつけて、帯にはさんで携帯しました。
蒔絵などの細工が施されていて、粋な江戸っ子のファッションの一つとして、さりげないこだわりを入れていたようです。
以前の携帯電話のストラップのような感じでしょうか。
もともとはその名のとおり、印鑑(いんかん)の篭(かご)で、印判、印肉と呼ばれる、現代のハンコなどを入れるものでしたが、江戸時代には薬を入れて携行するのに用いたそうです。
まとめ
このように、旅の道具は見ているだけで楽しいですね。
昔も、物見遊山(ものみゆさん)として旅をしていたでしょうから、用意をしているだけで、楽しくて、寝れない夜もあったと思います。
道具を調べていると、いろいろ試行錯誤したようなこだわりなどを見ていると、現代も昔も人間の考えていることは同じだなとつくづく思いました。
楽しい調べものでした。
おしまい。
参考:KAWADE夢文庫「こんなに面白い江戸の旅」
参考:よみがえった箱根関所
http://www.hakonesekisyo.jp/
参考:宮崎県埋蔵文化財センター
http://www.miyazaki-archive.jp/maibun/chishiki/hiuchiishi.html
参考:明宝歴史民俗資料館
http://dac.gijodai.ac.jp/vm/virtual_museum/database/page2/0787-0005m.html
参考:たばこと塩の博物館
https://www.jti.co.jp/Culture/museum/collection/tobacco/t13/index.html